
突然やってくる悲しみの儀式である葬儀、いざとなったときに慌てることのないよう、事前に知っておくと良いことがたくさんあります。その一つが葬儀に出席する際の服装です。
ここではその中でも「着物」を着るときのルールやマナーについてみていきましょう。
喪服の格式と着用できる人の制限は
和装洋装を問わず、喪服は格式によって「正喪服」「準喪服」「略喪服」という3種類に分かれています。
「正喪服」は、男性の場合なら喪主をはじめとして遺族や親族だけが着用するものです。女性は喪主となった人がお通夜の席から着用するのが一般的です。
「準喪服」は喪主以外の遺族と親族、及びごく近しい関係の人が着用するもので、お通夜・告別式・四十九日・一周忌など、どの場面でも着用できます。女性の場合、喪主以外の遺族と親族が着用します。
「略喪服」は訃報を聞いて急遽かけつける場合や、一般的な会葬に参列する場合に着用します。女性ならば一般会葬への参加や、地域の葬式などに出席するときに使用します。
正喪服を着ることができる人には範囲があり、一般的には三親等までとされています。喪主をはじめ、遺族・親族、葬儀委員長は喪に服する立場であるため、通夜から葬儀・告別式まで男女とも正喪服を着用することになります。
ただし場合によっては故人の親友や親しかった知人も正喪服を着ることがあります。
正喪服にはどんな決まりごとがあるのか
男性の正喪服は、黒羽二重仕立てで染め抜きされた五つ紋付きの長着と羽織を着て、仙台平又は博多平の袴をつけます。羽織の紐には黒かグレー、半襟と長襦袢は白か黒かグレーのものを用います。
帯は地味な色の角帯で、足袋は黒か白、草履は畳表付の鼻緒の色が黒か白のものになります。また、扇子は弔事の場合は必要がありません。
女性の正喪服は、黒無地染め抜き五つ紋付きの着物を着用し、生地は関東の場合は黒の羽二重、関西では黒の一越縮緬を用いるのが一般的です。
半襟と長襦袢の色は白、帯は黒の袋帯あるいは名古屋帯を使います。格式が高いとされるのは名古屋帯よりも袋帯なのですが、地域によっては袋帯は悲しみの席にふさわしくないとされる場合もありますので、注意が必要です。
袋帯を用いる際には不幸が重なるといわれる二重太鼓ではなく一重太鼓結びをします。帯締めは黒色の平打ち又は丸くげ、足袋は白、草履は黒色の布製のものか畳表付き鼻緒が黒のものを用います。髪飾りや帯止めは必要ありません。
葬儀で着物を着るときの女性の髪型やメイクは
葬儀で着物を着用するときには、ヘアスタイルは小さめにまとめることが基本です。葬儀の席ではお辞儀をすることも多いため、髪が落ちてこないように気をつけましょう。
長い髪をアップにする際はなるべく低めの位置でまとめ、セミロングなら耳の位置あたりに目立たないようピンで留めておくと良いです。
化粧は薄化粧を心がけ、華やかさが出ないようルージュは薄めの色にとどめてください。アイシャドウはきらきらするものは避けて、チークは使用しないか、付けるならあまり目立たない肌なじみの良いものが好ましいです。
アクセサリーは結婚指輪以外のものは原則付けないのがマナーとなります。
またふだん香水を付ける習慣のある方は、当日は注意しましょう。多くの方が集まるしめやかな席では香りへの配慮はとても大切です。
葬儀・告別式で着物を着用する際にはさまざまなマナーがあります。まず和装の喪服には格式があり、葬儀の主催者になった場合には参列者よりも格式の高いものを身に付けるのがルールです。
特に正喪服の場合は、羽織・袴や帯、和装小物の素材や色などにも細かい決まりごとがありますので注意しましょう。また女性の場合はヘアスタイルや化粧などにも配慮が必要です。中野区の葬儀で着物を着用するにあたりそれらの決まりごとを守れば、参列者への礼を欠くこともなく大切な儀式を執り行うことができるでしょう。
-
 引用元:https://www.iumemory.co.jp/
引用元:https://www.iumemory.co.jp/
アイユーメモリーは死後事務委任契約で面倒な手続きの一切を請け負いトータルでサポート。24時間365日いつでも相談可能!葬儀当日を想定した見積もりが分かりやすい葬儀屋さんです。
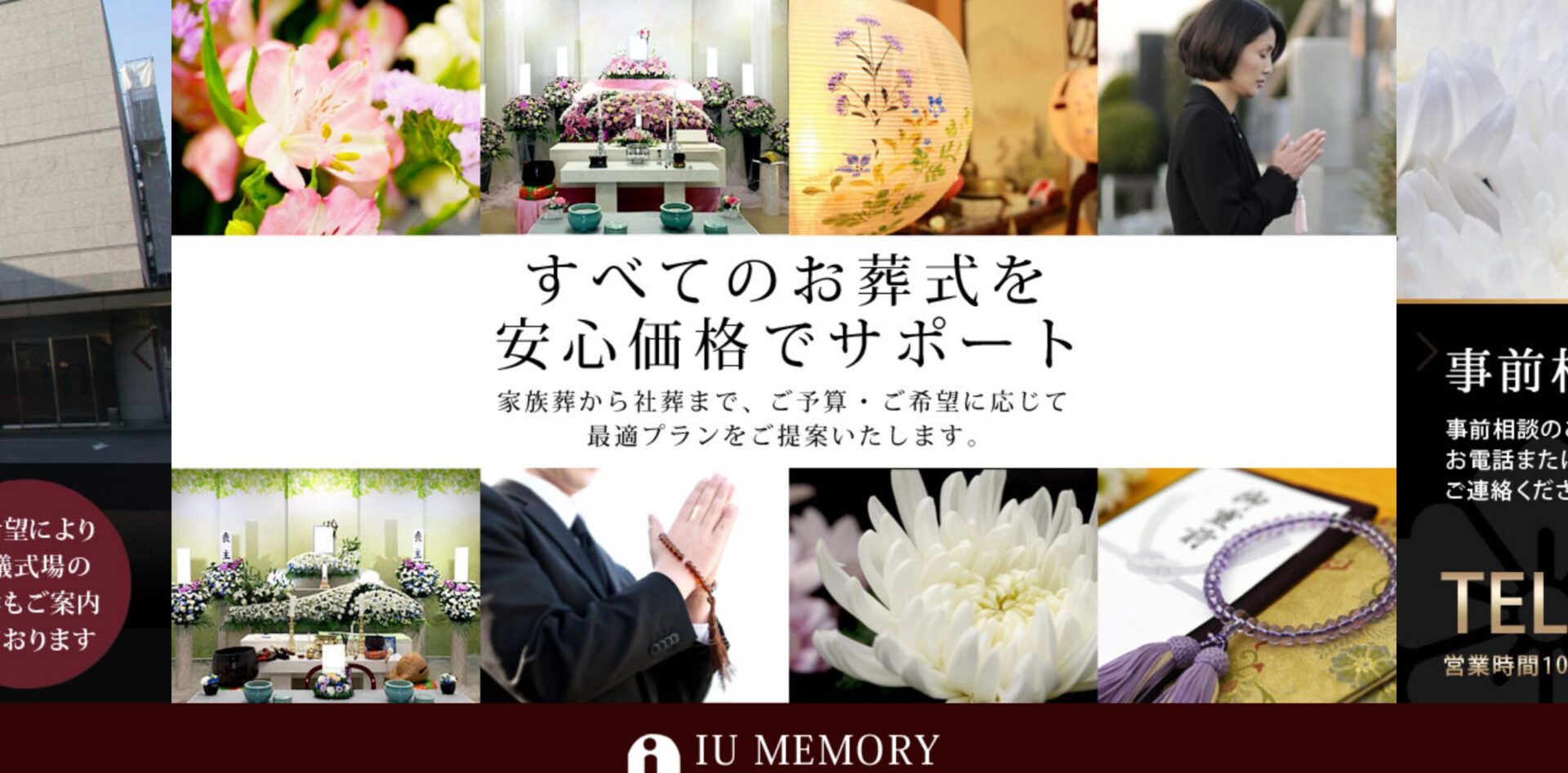
 アイユーメモリー
アイユーメモリー 
 あすなろ葬祭
あすなろ葬祭 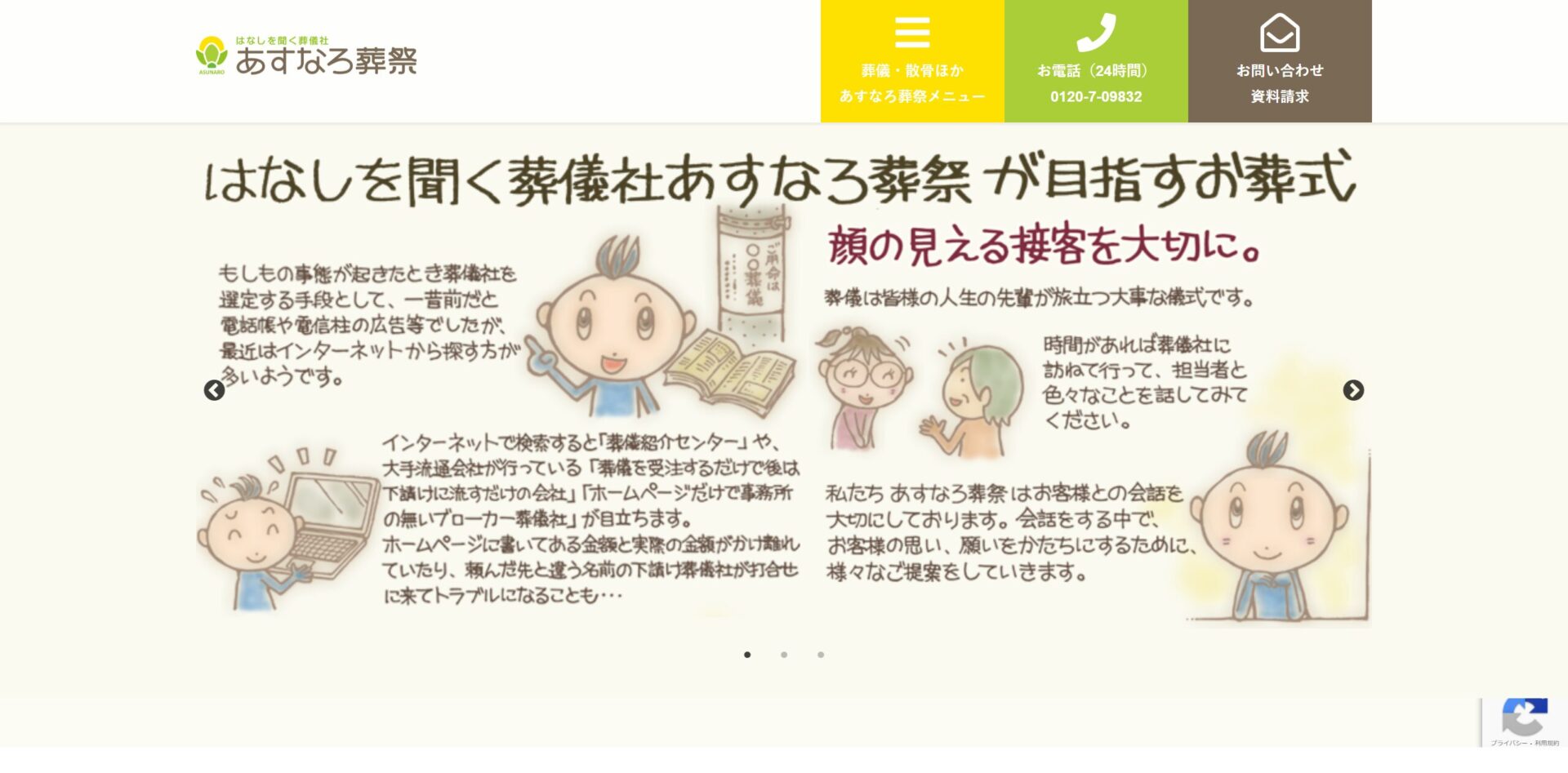
 花葬儀
花葬儀 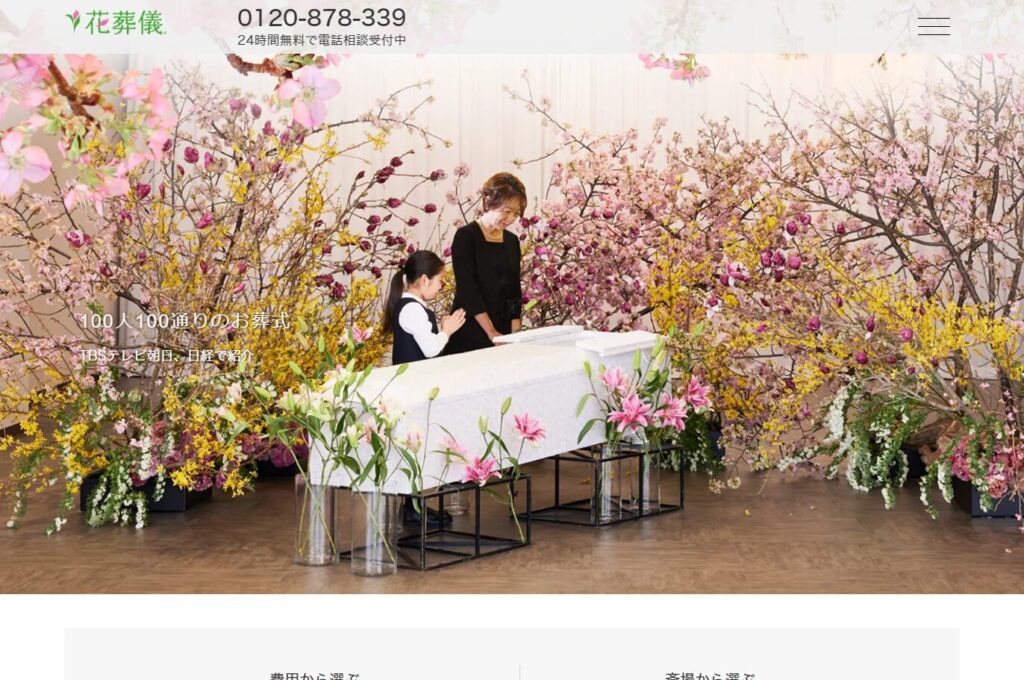
 グランドセレモニー
グランドセレモニー 
 むすびす(旧アーバンフューネス)
むすびす(旧アーバンフューネス) 









