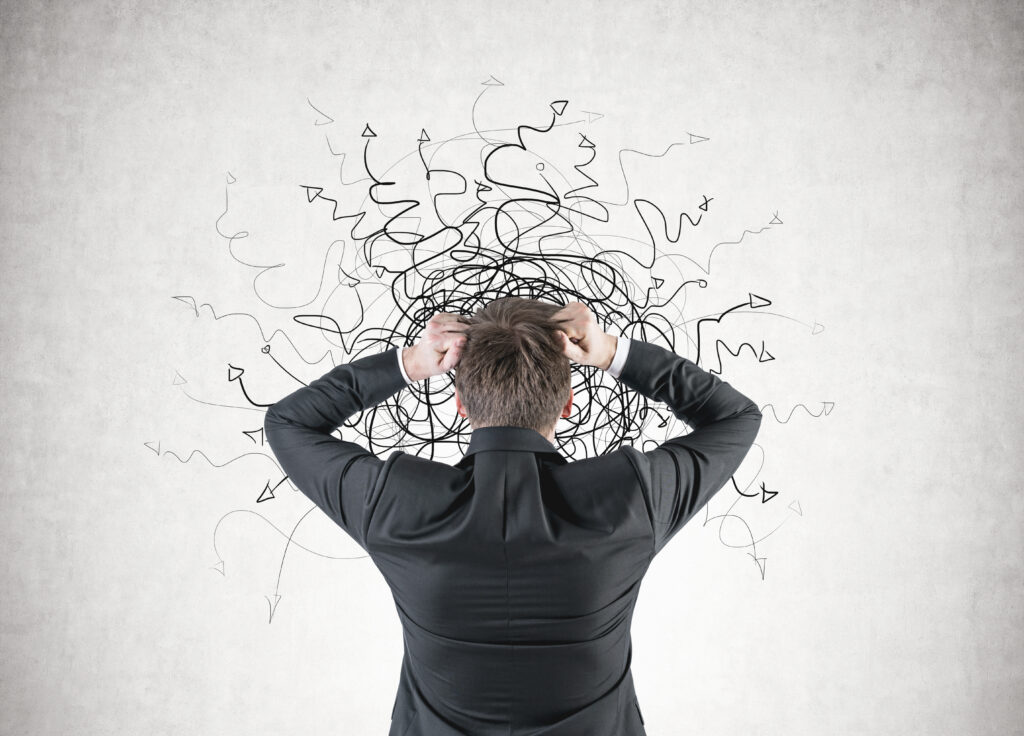
もし今日亡くなった場合、葬儀はいつになるのでしょうか?多くの人が知っているようで、いざ直面すると不安が募る場面です。この記事では、亡くなってから葬式が行われるまでの日程や、それを決めるための基準、準備の流れについてわかりやすく解説します。葬儀はいつになるのか知りたい方は、参考にしてみてください。
亡くなってから葬儀までの一般的な流れ
人が亡くなってから葬儀が行われるまでのスケジュールは、地域の風習や遺族の意向によって異なりますが、一般的には亡くなった日から3日から7日以内に執り行われます。
葬儀の日程は遺族の準備状況、僧侶や会場の都合、親族のスケジュールなどによって調整されます。
診断書や死亡届の提出
最初に、医師から死亡診断書を受け取り、役所に死亡届を提出する必要があります。
これにより、正式に死亡が認められ、火葬許可証を取得できます。この手続きは、葬儀会社が代行することも可能です。
お通夜の実施
多くの場合、葬儀の前夜にはお通夜が行われます。
お通夜は、故人を偲び、親しい人々が集まって最後の夜を一緒に過ごします。お通夜の日程は、亡くなってから2~3日後に設定されることが一般的です。
葬儀・告別式
お通夜の翌日には、正式な葬儀と告別式が行われます。
ここでは、故人を送り出すための儀式や弔辞、参列者からの供養が行われます。式の後には、火葬場へ移動し、故人の体を火葬に付します。
葬儀の日程を決める際の基準
葬儀の日程は、さまざまな要因を考慮しながら決める必要があります。
すべての遺族や関係者が都合よく参列できる日を調整するのは難しい場合もありますが、以下のポイントを基に計画を進めるとスムーズです。
遺族の意向や体調
亡くなった直後は、遺族も精神的に動揺していることが多いため、無理をせず、体調や心の負担を考慮して日程を決めることが大切です。
葬儀は急いで行わなければならないものではなく、数日間の猶予がある場合が多いため、冷静に考えることが求められます。
参列者のスケジュール
親族や友人、関係者の多くが参列できる日程を選ぶことが理想的です。
とくに、遠方からの参加が見込まれる場合は、移動にかかる時間や手間を考慮し、週末や祝日を選ぶこともひとつの方法です。
会場や僧侶の都合
葬儀を行う会場や僧侶のスケジュールによっても日程が左右されます。
とくに繁忙期や特定の宗教的な儀式が必要な場合は、早めの予約や調整が必要です。人気の会場や僧侶の場合、日程が制限されることも多いため、迅速な判断が求められます。
葬儀の準備に必要な手続きと流れ
葬儀の準備には、さまざまな手続きと段取りが必要です。
これらの作業をしっかりと進めることで、スムーズに葬儀を執り行うことができます。葬儀会社を利用すれば、多くの手続きや段取りをサポートしてもらえるため、事前に相談することをおすすめします。
遺族との打ち合わせ
まずは、遺族や親族と葬儀の規模や形式、予算などについて打ち合わせを行います。
葬儀の内容を決定した後、会場の予約や僧侶の手配を進めていきます。葬儀会社のプランには、基本的なセットが用意されていることが多いため、それに基づいて調整を行うことも多いです。
火葬や納骨の手続き
葬儀の後は、故人を火葬に付し、その後は納骨や散骨などの手続きを行います。
火葬場の予約や、墓地の手配などは事前に進める必要があります。また、宗教によっては特定の儀式が行われることもあるため、事前に確認が必要です。
通夜・告別式の進行準備
通夜や告別式の進行に必要な道具や設備の準備も進める必要があります。
葬儀の進行は葬儀会社が担当することが多いですが、家族の希望や意向を伝えて、スムーズに進行できるようにしましょう。お花の手配や参列者への案内状の準備も欠かせません。
まとめ
亡くなった直後は、葬儀の日程や準備に関して多くのことを考える必要がありますが、遺族の負担を減らすためにも、落ち着いて進めることが大切です。お通夜や葬儀の日程は、遺族や参列者、会場の都合などを考慮しながら決定され、3日から1週間程度が一般的なスケジュールとなります。葬儀会社や周囲のサポートをうまく活用しながら、適切な手続きを進めましょう。
-
 引用元:https://www.iumemory.co.jp/
引用元:https://www.iumemory.co.jp/
アイユーメモリーは死後事務委任契約で面倒な手続きの一切を請け負いトータルでサポート。24時間365日いつでも相談可能!葬儀当日を想定した見積もりが分かりやすい葬儀屋さんです。
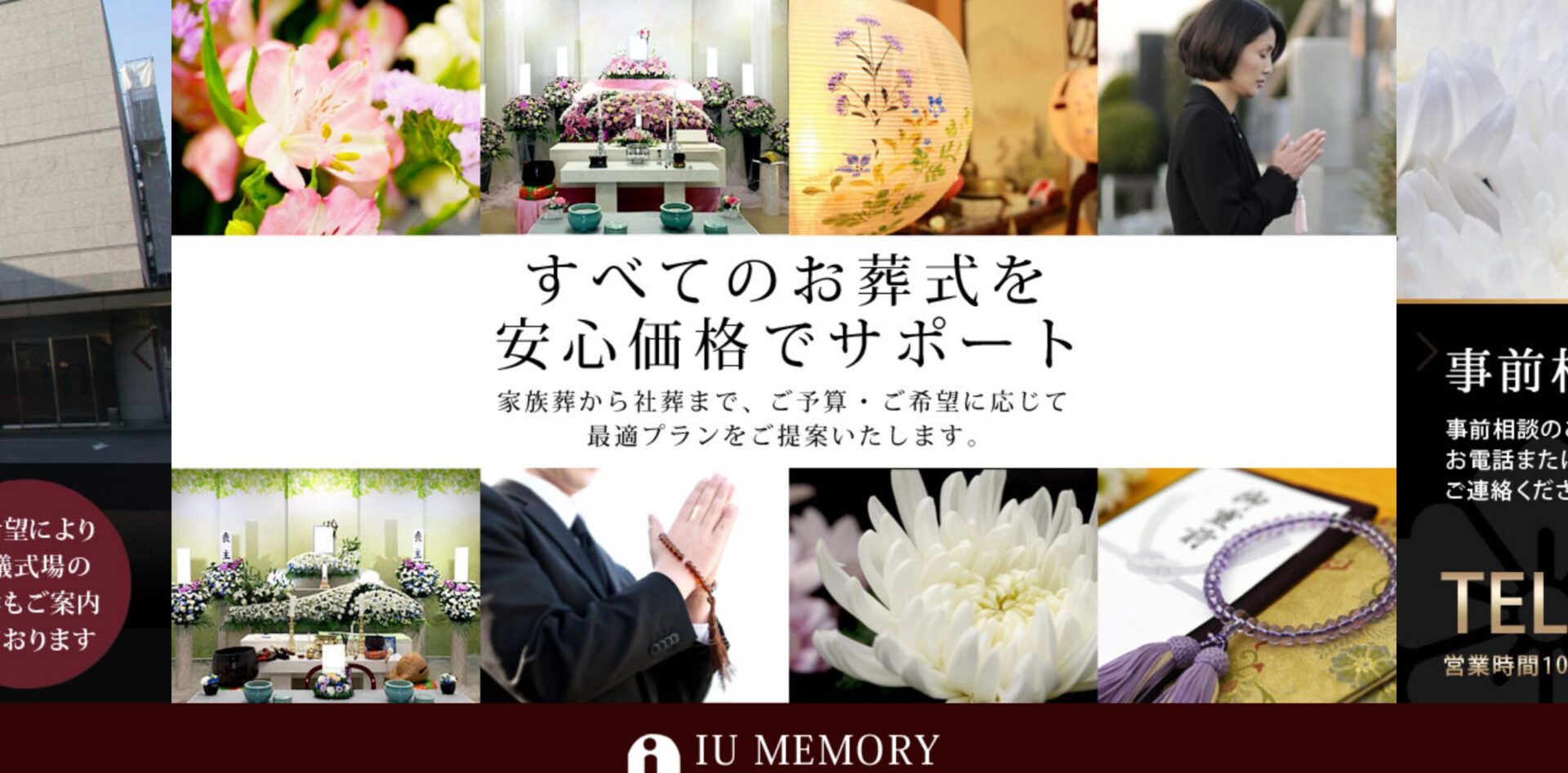
 アイユーメモリー
アイユーメモリー 
 あすなろ葬祭
あすなろ葬祭 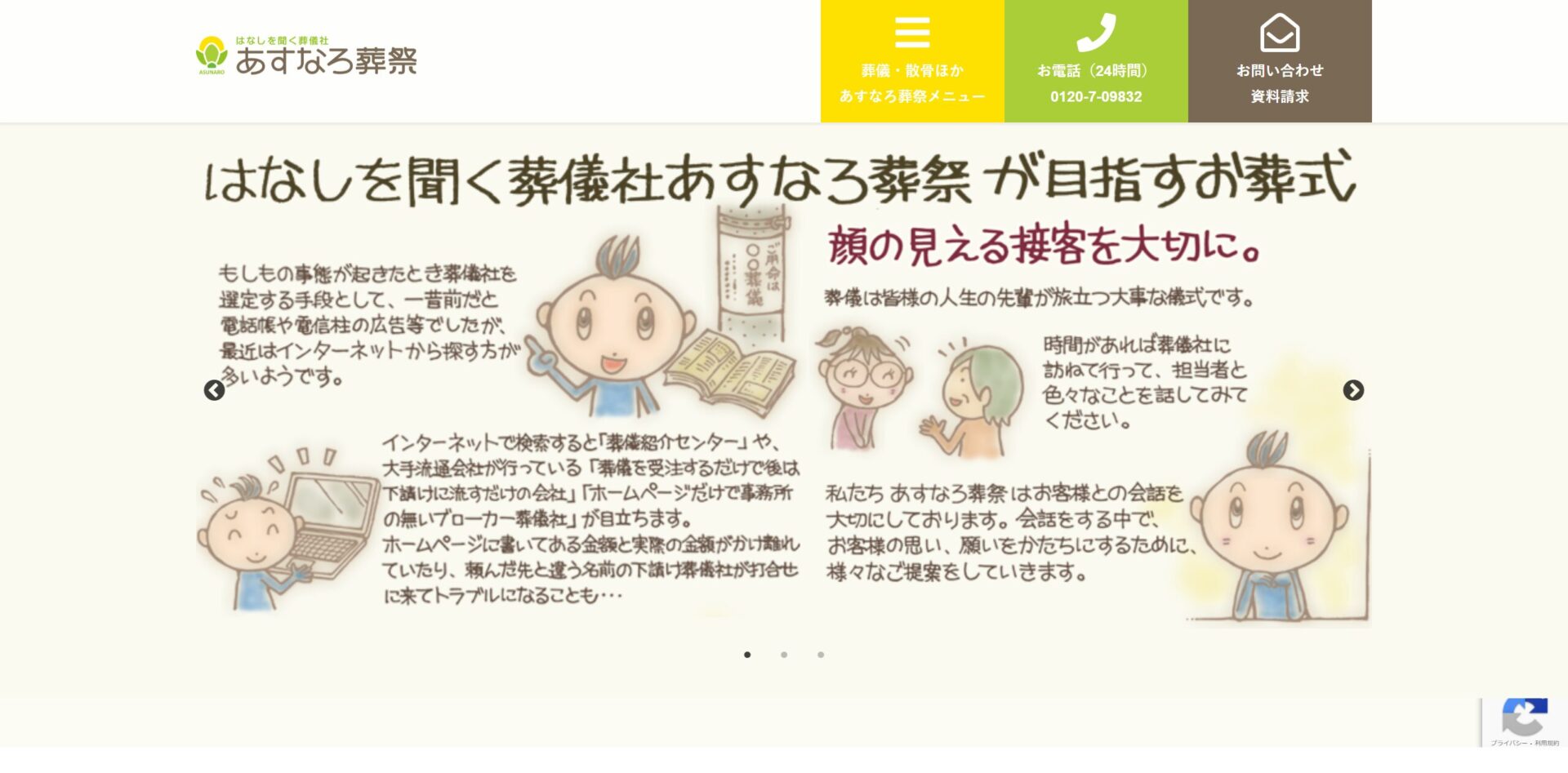
 花葬儀
花葬儀 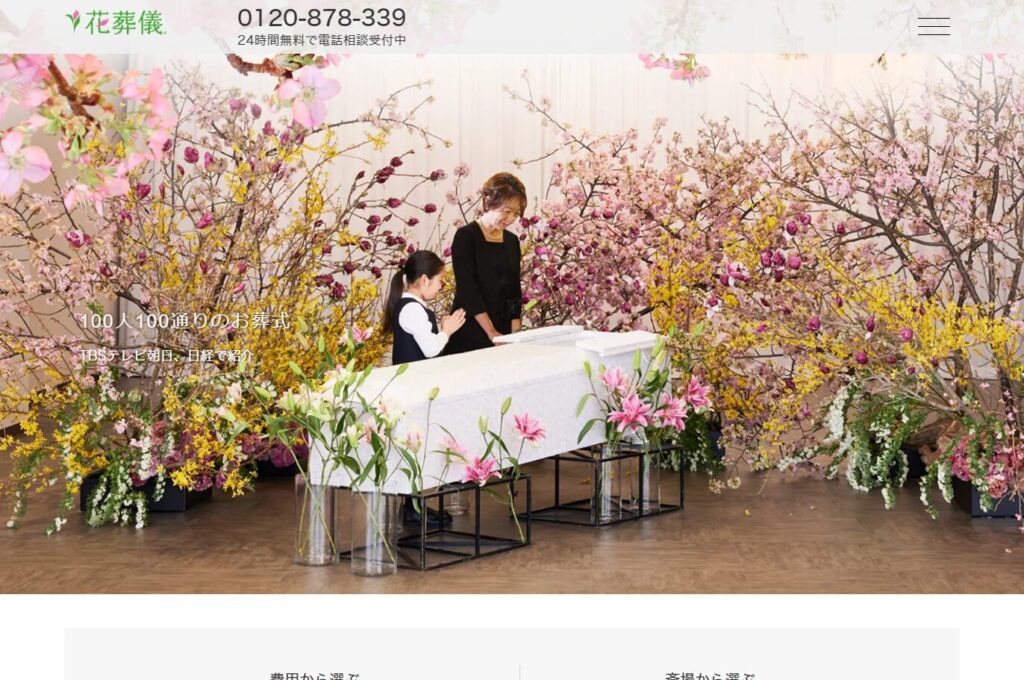
 グランドセレモニー
グランドセレモニー 
 むすびす(旧アーバンフューネス)
むすびす(旧アーバンフューネス) 









