
焼香は、仏式葬儀において重要な儀式の一つです。その作法や流れを理解しておかないと、葬儀に参列する際に遺族や故人に対して失礼となる可能性があります。本記事では、焼香の基本的な作法や流れ、さらに宗派ごとの焼香の回数について詳しく解説します。これを参考に、焼香の手順を学び、必要な場面で落ち着いて対応できるようにしましょう。
CONTENTS
焼香の作法・流れ
焼香の作法は、宗派によって若干の違いはありますが、共通して大切なのは故人の冥福を心を込めて祈ることです。
基本的な焼香の手順は、まず右手の親指、人差指、中指の3本(または親指と人差指)で抹香を少量つまみ、手を返して額の高さまで掲げます。この際、手を高く上げて「押しいただく」動作を行います。
その後、香炉の近くに進み、香炉に抹香をこすりながら静かに落としましょう。手順の間、左手には数珠をかけておきます。
焼香の流れ
焼香の流れは、葬儀の際に僧侶が入場し、読経が始まると、順番に焼香を行うことになります。
焼香の順番は「喪主・遺族・親族・一般弔問客」の順に進みますが、名前を呼ばれることはなく、前の人が席に戻った後に行うのが一般的です。焼香を行う際は、まず焼香台の前に進み、遺族に一礼をします。その後、焼香台に進み、故人の遺影に向かって再度一礼し、焼香台の前に立ちます。
そして左手に数珠をかけ、右手の親指、人差指、中指で抹香をつまみ、額の高さまでかかげましょう。この「押しいただく」動作をした後、抹香を香炉に静かに落とします。抹香を落とす際は指をこすりながら、静かに行うことが大切です。
焼香後は、両手に数珠をかけて合掌し、その後少し下がって遺族の方へ一礼します。最後に、席に戻る際も一礼をし、焼香の儀式を終えます。焼香はただの儀式ではなく、故人への尊敬と感謝の気持ちを込めた重要な行為です。心を込めて、静かに行うことが大切です。
宗派ごとに焼香の回数は異なる
仏教には多くの宗派があり、それぞれに焼香の作法があり、回数にも違いがあります。
焼香の作法は、葬儀において宗派ごとに異なりますが、必ずしもその作法に厳密に従うことが求められるわけではありません。
基本的には、葬儀の主催者や参列者がその宗派の作法に則ることが一般的ですが、過剰にマナーを心配する必要はありません。各宗派ごとの焼香の回数について詳しく見ていきましょう。
天台宗
まず、天台宗では、とくに焼香の回数に決まりはありません。
焼香を行う際は、心を込めて故人を偲ぶことが最も大切とされています。
真言宗
真言宗では、焼香は3回行い、押しいただく動作を含めて慎重に行います。
浄土宗
浄土宗では、押しいただきの回数は1回から2回の間で行われます。どちらも、故人に対する敬意を示しつつ、静かに行われることが大切です。
浄土真宗
浄土真宗には2つの派があり、本願寺派では押しいただきはせず、焼香は1回のみ行います。一方、東本願寺派では、焼香を2回行い、こちらも押しいただく動作はありません。
臨済宗
臨済宗では、焼香は1回行いますが、押しいただくかどうかは定めがなく、自由に行われます。
曹洞宗
曹洞宗では、2回焼香を行います。1回目は押しいただき、2回目はそのまま抹香を香炉に落とす作法です。
日蓮宗
最後に、日蓮宗では、焼香の回数は1回または3回のいずれかで行われ、押しいただくこともあります。
まとめ
焼香は仏式葬儀の重要な儀式で、故人に対する敬意と冥福を祈る行為です。基本的な作法は、抹香をつまんで額の高さまで掲げ、「押しいただく」動作を行い、その後香炉に静かに落とすことです。焼香の順番は、喪主・遺族・親族・一般弔問客の順で行われ、名前を呼ばれることはありません。宗派ごとに焼香の回数に違いがあり、たとえば真言宗では3回、浄土宗では1〜2回、浄土真宗では1回または2回など、細かい作法の違いがあります。しかし、重要なのは心を込めて故人を偲ぶことです。宗派の作法を過剰に心配することなく、静かに心を込めて焼香を行うことが大切です。
-
 引用元:https://www.iumemory.co.jp/
引用元:https://www.iumemory.co.jp/
アイユーメモリーは死後事務委任契約で面倒な手続きの一切を請け負いトータルでサポート。24時間365日いつでも相談可能!葬儀当日を想定した見積もりが分かりやすい葬儀屋さんです。
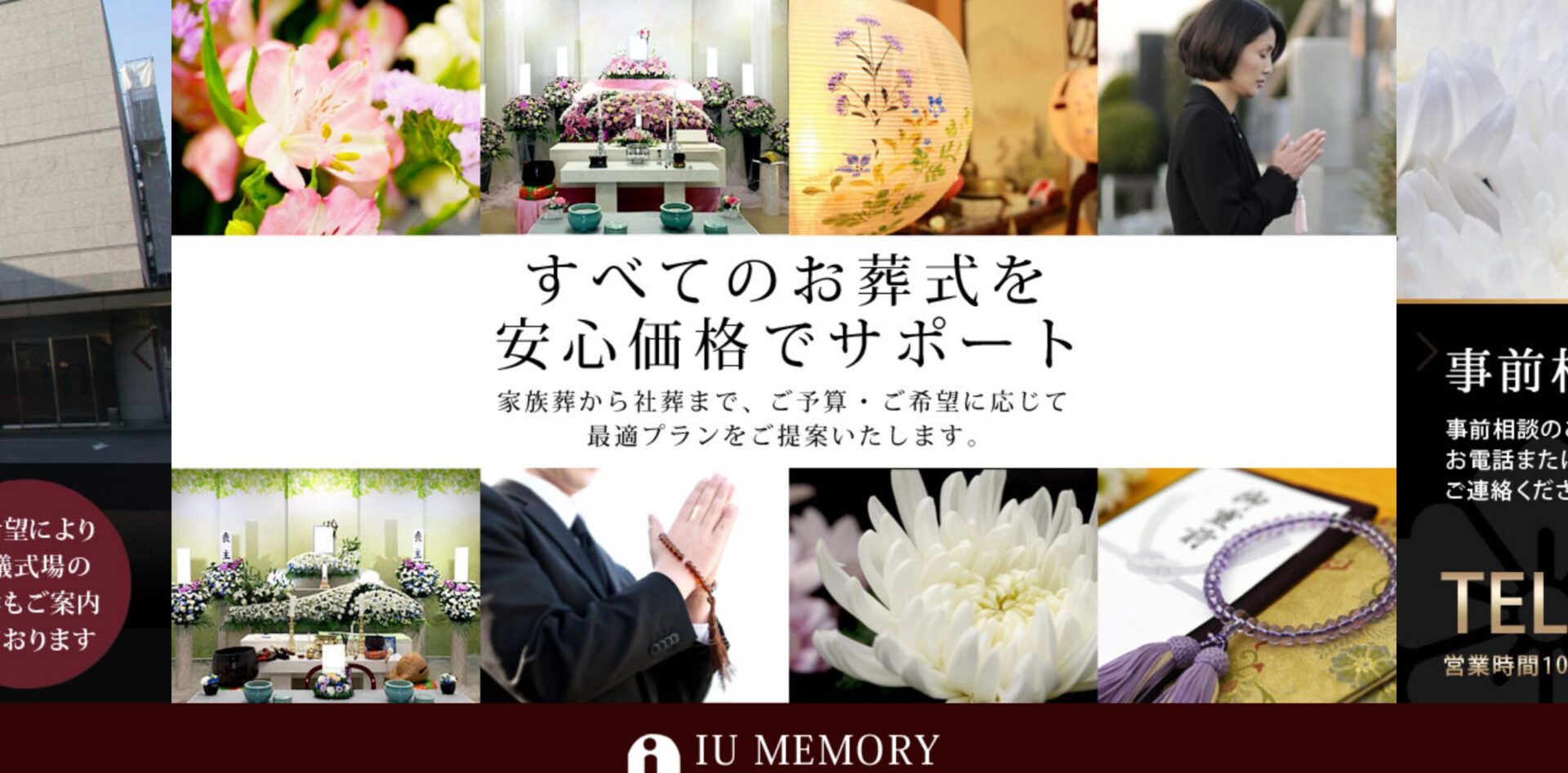
 アイユーメモリー
アイユーメモリー 
 あすなろ葬祭
あすなろ葬祭 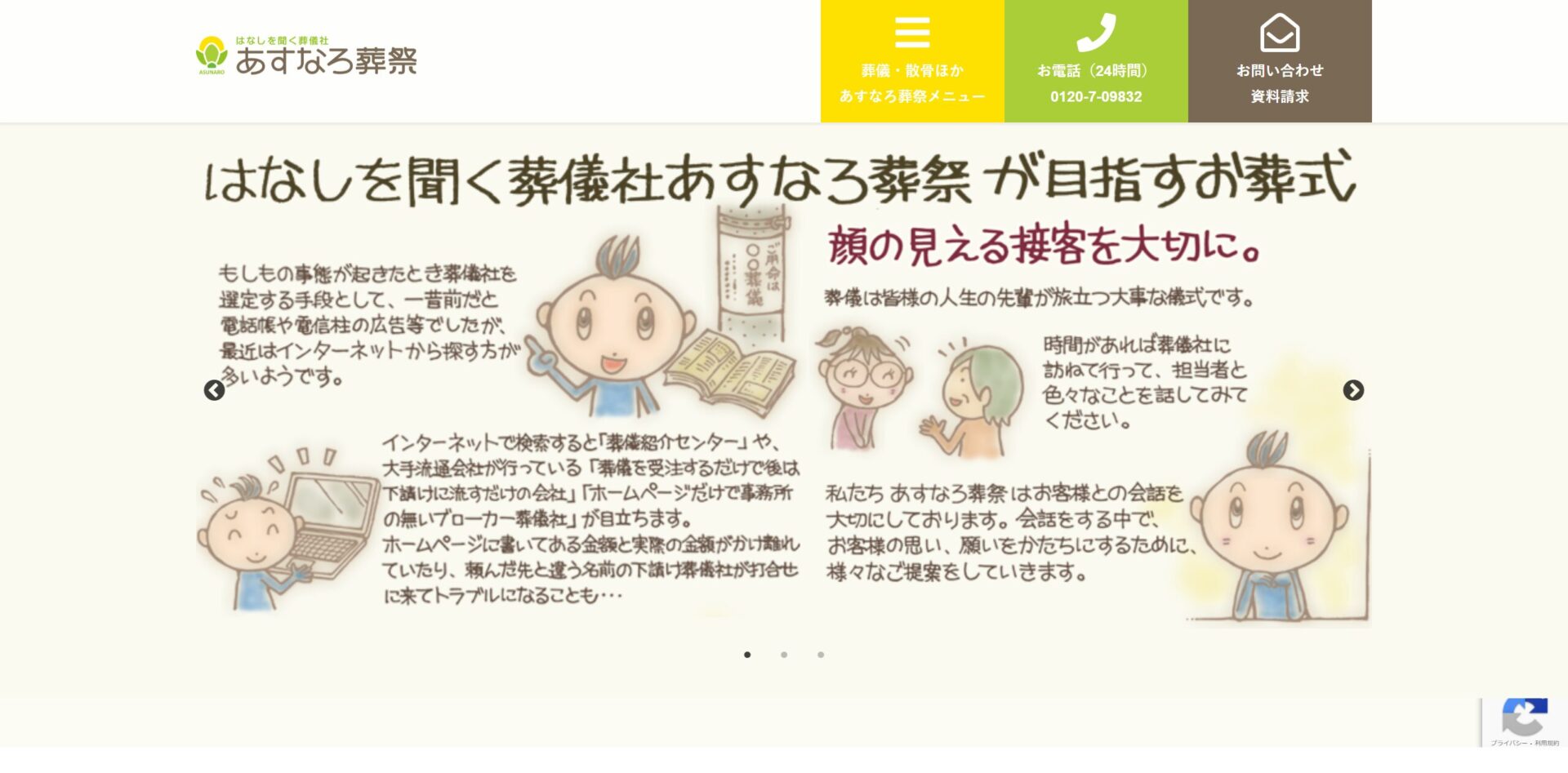
 花葬儀
花葬儀 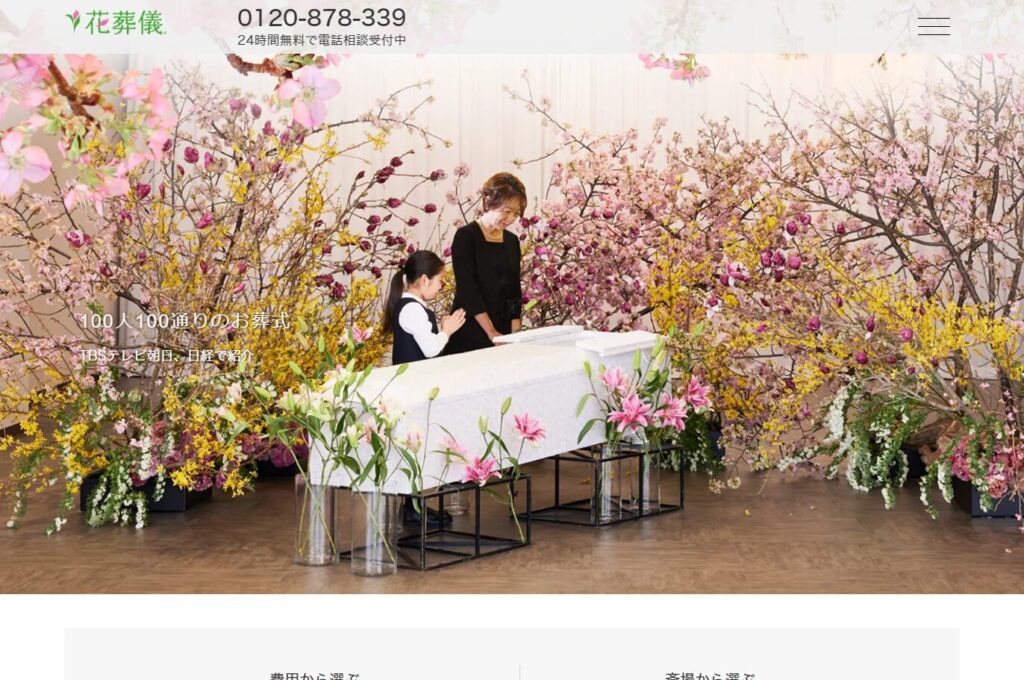
 グランドセレモニー
グランドセレモニー 
 むすびす(旧アーバンフューネス)
むすびす(旧アーバンフューネス) 









