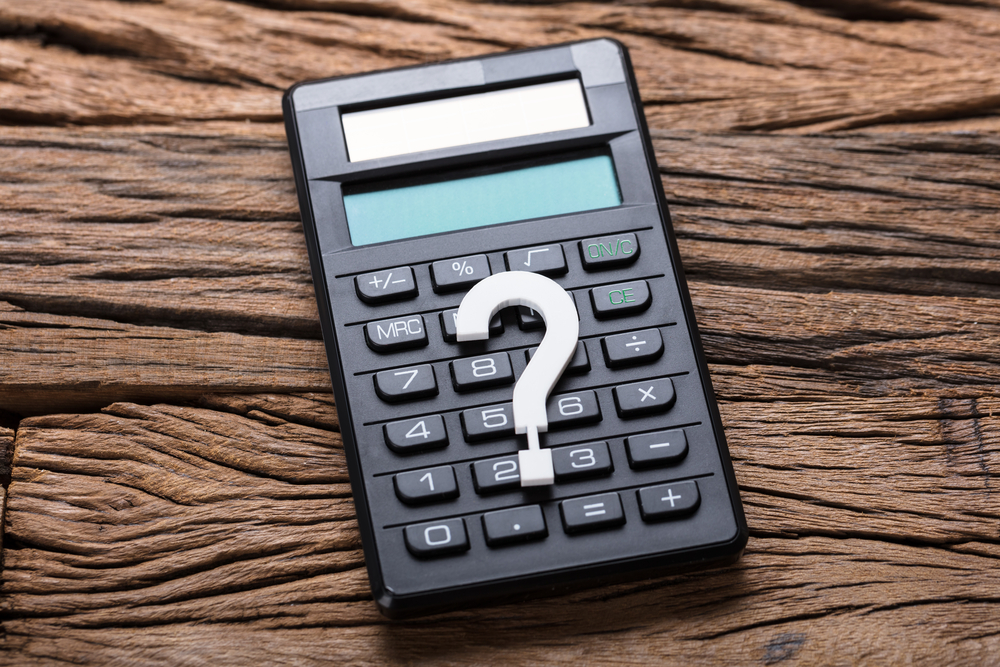大切な人が亡くなった際、お通夜やお葬式の日程がいつになるのか、また「友引」の日が葬儀にどのように影響するのか、知っておくことは重要です。この記事では、一般的な流れや友引にまつわる習慣、さらに友引を含む場合の対策について詳しく説明します。お通夜やお葬式の日程を知りたい方は、参考にしてください。
お通夜とお葬式の基本的な日程について
お通夜とお葬式の流れは、故人が亡くなってから数日以内に行われるのが一般的です。
具体的な日程は地域や宗派、また故人の家族の事情によって異なることがありますが、通常は以下の流れで進行します。
お通夜は亡くなってから1~2日後
お通夜は、故人が亡くなってから1日目もしくは2日目に行われることが多いです。
お通夜は、故人との最後の別れを惜しむための場であり、主に故人と親しい人々が集まります。この場では、故人を偲ぶ時間を持ち、供養を行います。お通夜のタイミングは基本的に亡くなった日の翌日ですが、家族の都合や施設の空き状況によって異なる場合もあります。
お葬式は亡くなってから2~3日後
お葬式は、一般的には故人が亡くなった2日目か3日目に行われます。
お葬式は故人を送り出すための重要な儀式であり、参列者が集まり、故人の冥福を祈ります。この儀式では、宗教的な儀礼が行われることが多く、地域や宗派によって式の進行や内容は異なる場合があります。お葬式が終わった後、遺体は火葬場に送られ、火葬が行われることが一般的です。
日程を決める際のポイント
日程を決める際は、家族や親族のスケジュール、参列者の移動時間、そして葬儀場や火葬場の空き状況なども考慮する必要があります。
とくにお盆や年末年始など、忙しい時期には葬儀場が予約でいっぱいになることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。また、地域によっては特定の日にお葬式を行わない風習があるため、地元の葬儀社と相談しながら決めることが望ましいです。
友引の日に葬儀を避ける理由とその対処法
「友引」という日は、古くからの風習として葬儀を避ける日とされています。
これは、友引が「友を引く」という意味を持つとされ、縁起が悪いとされているためです。では、友引の日に亡くなった場合、どう対応すれば良いのでしょうか。
友引の日の意味と由来
友引は六曜(ろくよう)の一つで、もともとは「友を引く」と解釈され、葬儀においては「友を連れて行ってしまう」という迷信が広まりました。
そのため、友引の日には葬儀を行わないことが一般的です。友引は陰陽道(おんみょうどう)や中国の占い文化から影響を受けており、日本でも長年にわたってこの考え方が続いています。
友引を避けるべきか
友引の日に葬儀を行わないという風習は、必ずしも法律や宗教的な教義に基づくものではなく、迷信に由来しています。
そのため、近年では友引の日でも葬儀を行うケースも増えています。しかしながら、依然として多くの地域や葬儀社では友引の日に葬儀を避ける習慣が残っています。とくに高齢者の参列者が多い場合、伝統的な風習を重んじて友引の日を避ける方が無難かもしれません。
地域や宗派による違い
お通夜やお葬式の日程や友引への対応は、地域や宗派によっても異なります。
たとえば、仏教では宗派によって友引を避けるべきかどうかが違い、また地域ごとに習慣が変わることもあります。
地域ごとの風習
地域によっては、友引の日でも葬儀が行われることが普通だったり、逆に特定の曜日や日付に葬儀を行わないという独自の習慣があったりします。
特に地方の風習が強く残るエリアでは、事前にその地域の慣習を確認しておくことが大切です。
宗派による違い
宗派ごとに葬儀やお通夜の進行や意味合いも異なります。
たとえば、浄土真宗では友引の日に葬儀を行うことが一般的であり、友引の日を気にしないという宗派も存在します。家族の宗派に従った進行が大切であり、葬儀社と相談しながら最適な対応を取ることが重要です。
まとめ
お通夜とお葬式は、故人が亡くなってから数日以内に行われるのが一般的ですが、日程は家族や参列者の都合、葬儀社の予約状況などに左右されることがあります。とくに「友引」の日に関しては、日本では古くからの風習として避けられることが多いものの、現代では柔軟に対応する家庭も増えています。地域や宗派による違いも加味し、重要なのは、故人を偲ぶ気持ちを最優先にし、家族や参列者が円滑に進行できるように配慮することです。
-
 引用元:https://www.iumemory.co.jp/
引用元:https://www.iumemory.co.jp/
アイユーメモリーは死後事務委任契約で面倒な手続きの一切を請け負いトータルでサポート。24時間365日いつでも相談可能!葬儀当日を想定した見積もりが分かりやすい葬儀屋さんです。
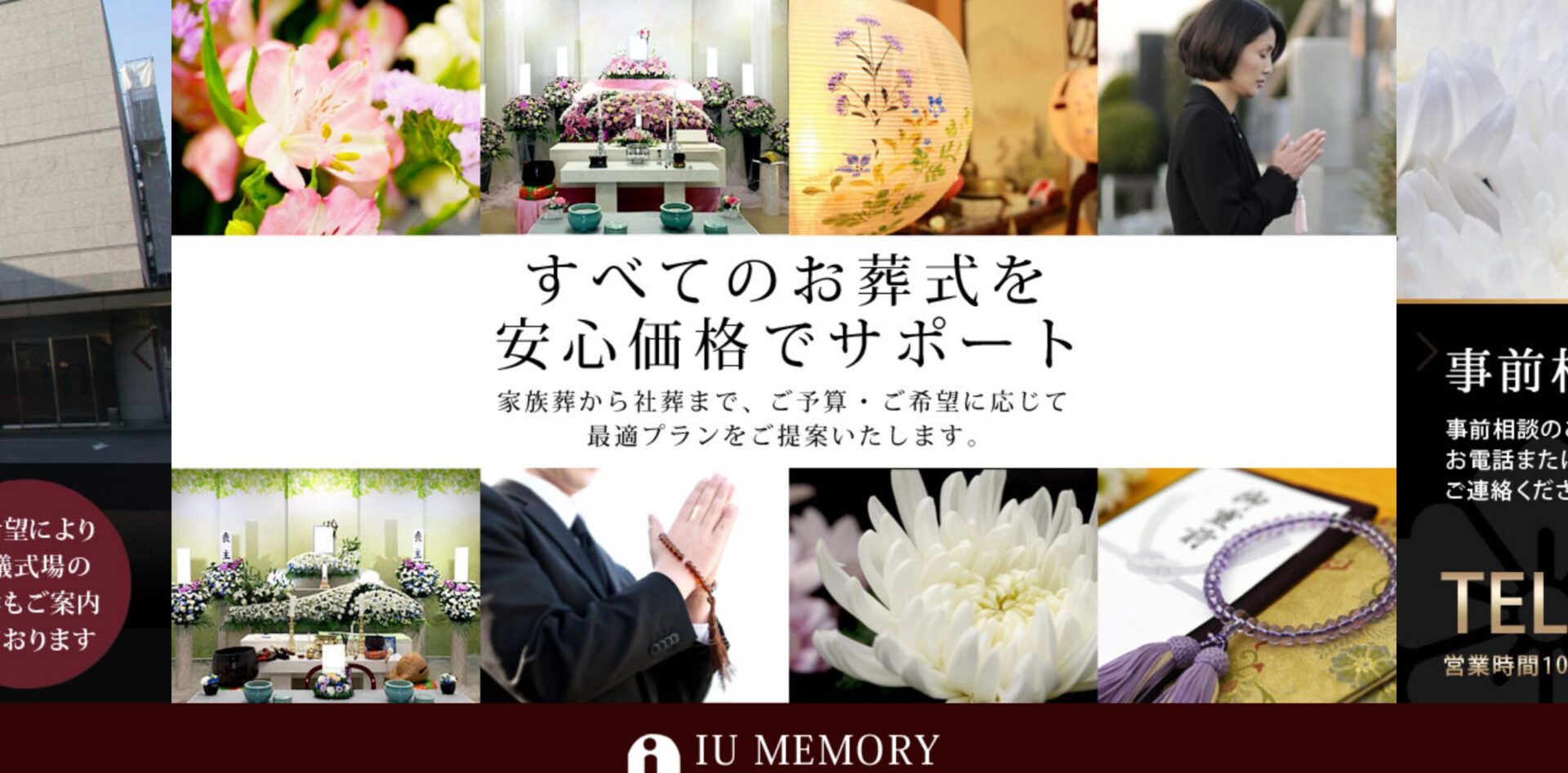
 アイユーメモリー
アイユーメモリー 
 あすなろ葬祭
あすなろ葬祭 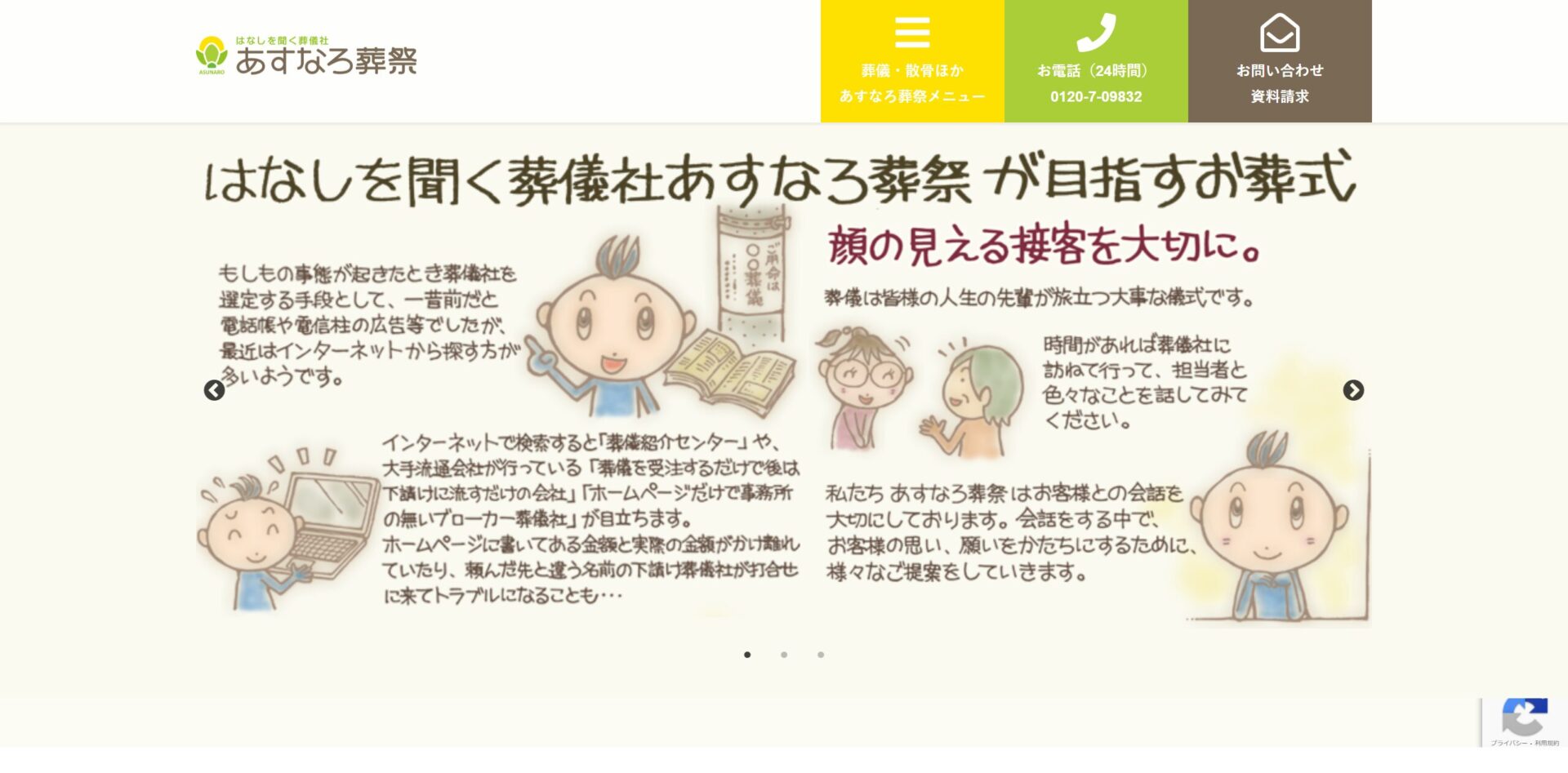
 花葬儀
花葬儀 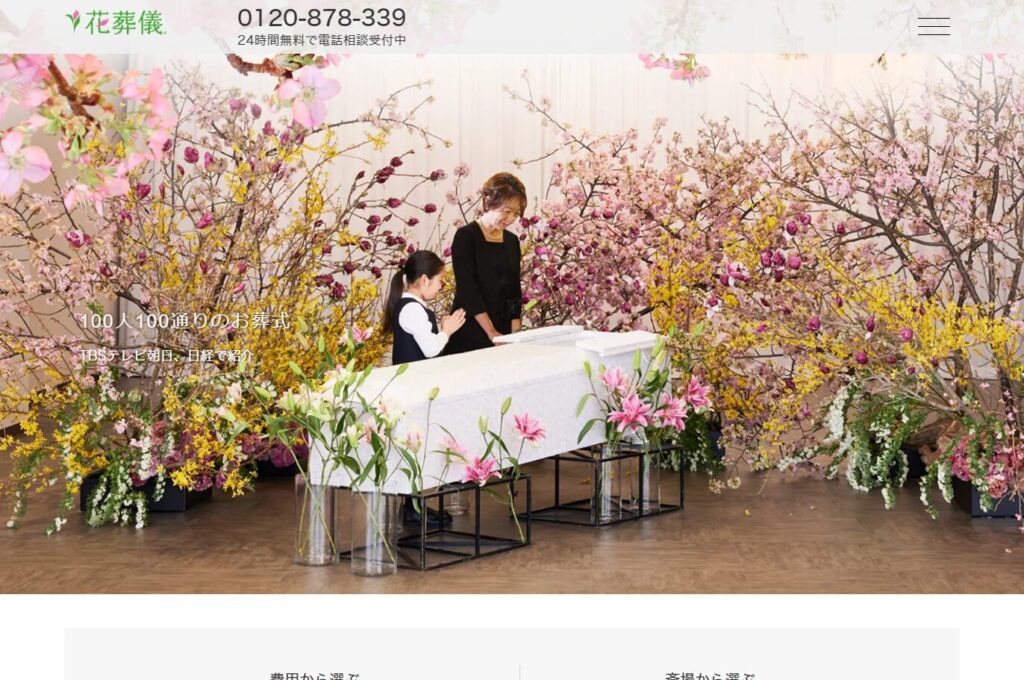
 グランドセレモニー
グランドセレモニー 
 むすびす(旧アーバンフューネス)
むすびす(旧アーバンフューネス)