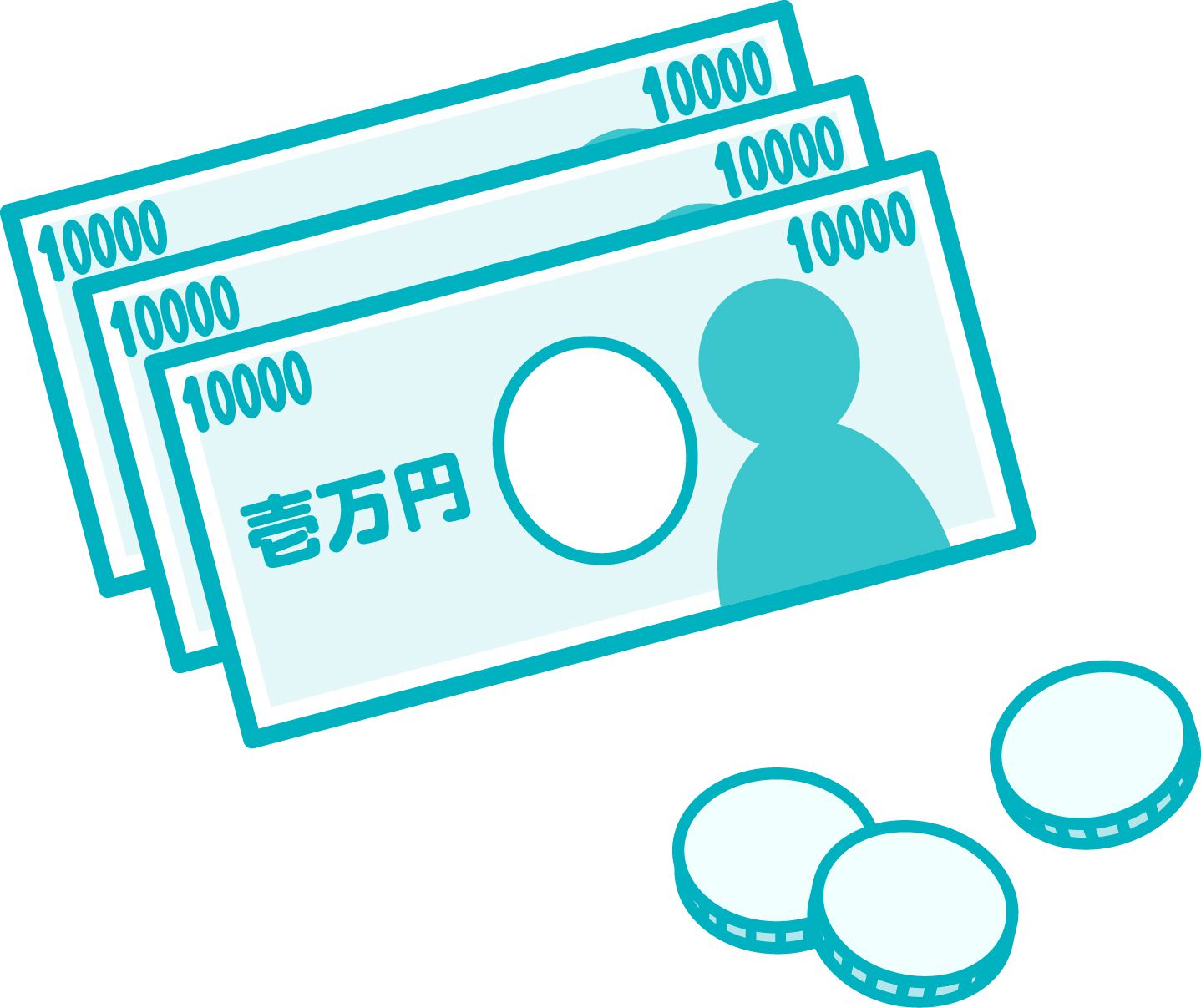家族が亡くなった後、何をすればいいのかわからない状態かもしれません。
業者に依頼をすればいろいろな対応をしてくれます。
自分で全て決めようとせず、相談しながら少しずつ予定を決めていきましょう。
ゆっくりし過ぎも行けません。
法律で火葬までに24時間以上あける必要がある
家族が亡くなるのは非常に寂しいことでしょう。
しかし現実を受け入れなければならず、その後にいろいろな法事などを行う必要があります。
自分たちで決めにくい時は、業者と相談をしながら日取りを決めると良いかもしれません。
〇葬儀を行うタイミング
では葬儀を行うタイミングはいつになるかです。
寂しいからと長く故人をそのままにしておくことはできません。
1日や2日だと見た目はほとんどわからないかもしれません。
でもどんどん腐敗が進んでいて、日が進めば見た目も変わってきます。
それを考えるとできるだけ早くした方がいいと考えるかもしれません。
一応法律で逝去から火葬までは24時間以上開けないといけないとされています。
医学的な見地で死亡が確認されれば一応はその時間が逝去の時間になりますが、万が一ということがあるかもしれません。
現実にはあまりないかもしれませんが、それを想定して一定の時間は火葬ができないことになっています。
逆に24時間後であればいつでも行えます。
慌てる必要はありませんが、24時間後に火葬ができる最も早いスケジュールで行うと良いかもしれません。
死亡届を出すと火葬の予約をすることができる
人に関わる変動があるときは、役所への届が必要です。
出生届や移動届などを出す機会があるでしょう。
そして亡くなれば死亡届を出す必要があります。
病院であれ自宅であれ、必ず医師の診断書が必要になります。
その診断書を元に届けを出しに行きます。
届に関しては、必ずしも家族が出さないといけないわけではありません。
比較的多いのは業者が代行するケースです。
遺族は落ち着いて役所で手続きができないときもあります。
死亡届を出すとき、一緒に行うのが火葬の予約です。
日本では人が亡くなると火葬しないといけない決まりになっていて、火葬場が営業しているときは火葬を行っています。
〇葬儀を行うタイミング
火葬の予約が取れた日を基準にすると良いでしょう。
亡くなる人が多い時期だと火葬の予約が埋まっていてすぐに火葬できない時があります。
又友引などがあると火葬場が休みになるため、行えません。
数日から1週間ぐらい先になることもあるので、遺体の保管方法などを業者に相談しなければいけません。
業者なら冷却して保管ができる施設などが利用できます。
檀家があるなら僧侶の予定を確認する
世界においては、多くの人が何らかの宗教の進行をしているとされています。
日本では古くから仏教を信仰する人が多いとされていますが、もちろんそれ以外の宗教を信仰している人もいます。
信仰深い人なら常にお寺などの行事などに参加したり、法事などで僧侶に依頼をしたりするかもしれません。
それぞれの家では、信仰している宗教のお寺と檀家や菩提寺としての関係を結ぶことがあります。
これによりそのお寺の墓地に入りやすくなったり、法事などを受けやすくなります。
〇葬儀を行うタイミング
檀家があるのであればそのお寺の僧侶の予定に合わせる時があります。
いつも来てもらう僧侶が他の法事で出かけているなら、その後の日に依頼するしかありません。
一方で檀家など特に宗教的なつながりがない時もあります。
この時は逆にどの僧侶に依頼したらいいのかわからなくて困るでしょう。
この時は業者に相談すれば、業者つながりの僧侶を教えてもらえます。
〇まとめ
人が亡くなると日本では火葬をする必要があり、その前に式などを行います。
火葬に関しては逝去から24時間以上経過しないといけない決まりになっているので、その決まりに従って火葬の予定を入れます。
その他僧侶の予定などを考慮します。
-
 引用元:https://www.iumemory.co.jp/
引用元:https://www.iumemory.co.jp/
アイユーメモリーは死後事務委任契約で面倒な手続きの一切を請け負いトータルでサポート。24時間365日いつでも相談可能!葬儀当日を想定した見積もりが分かりやすい葬儀屋さんです。
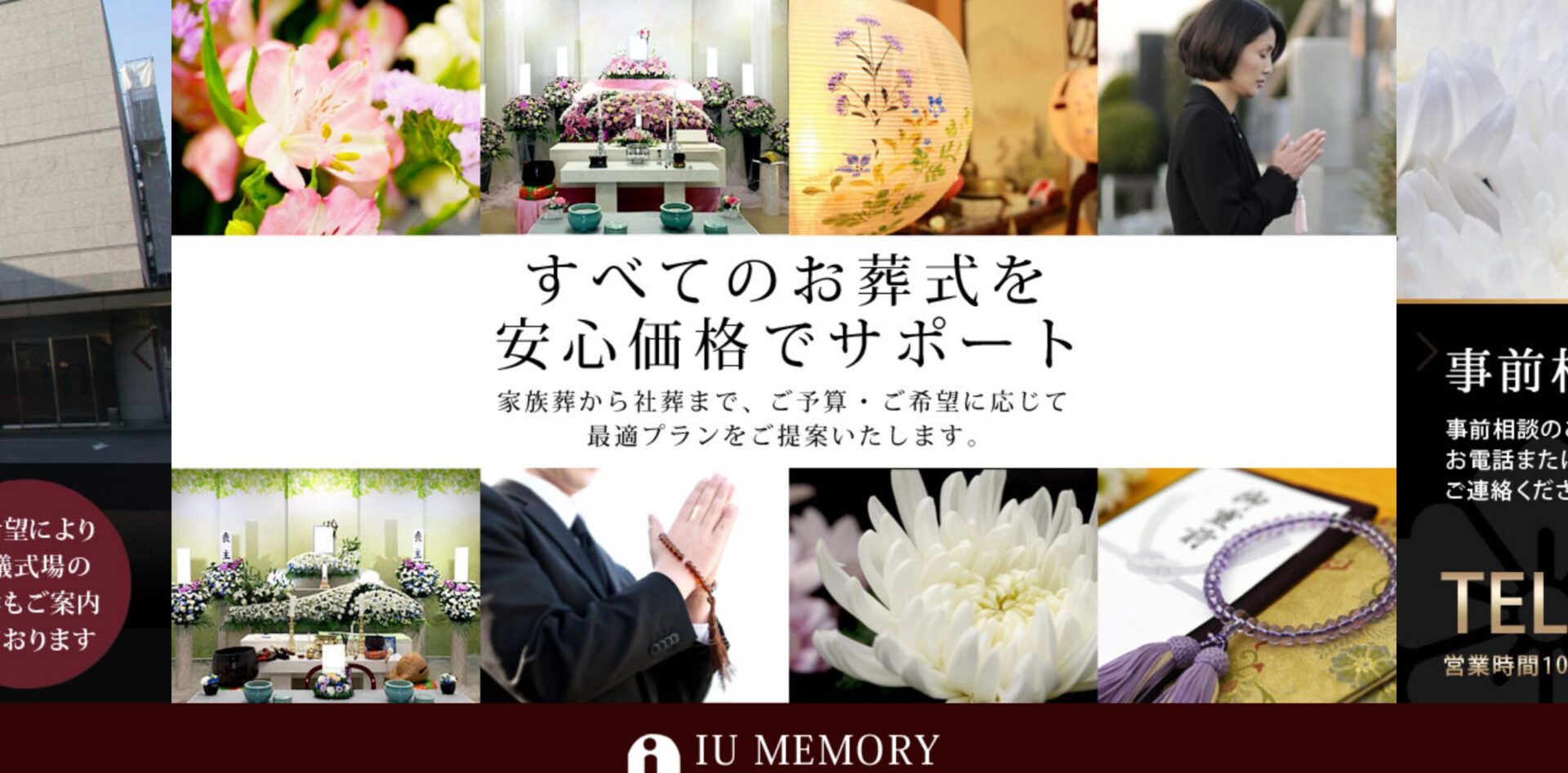
 アイユーメモリー
アイユーメモリー 
 あすなろ葬祭
あすなろ葬祭 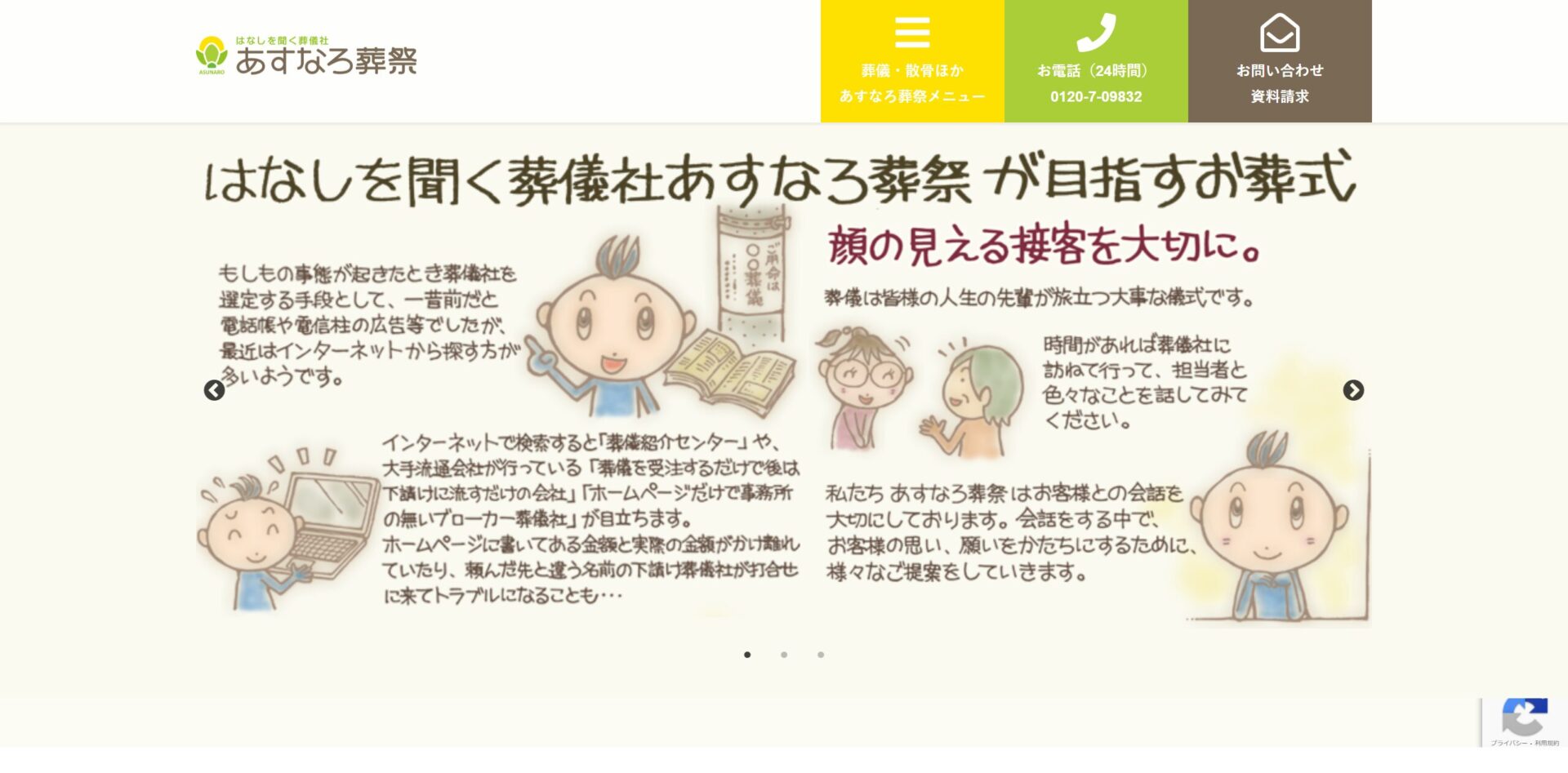
 花葬儀
花葬儀 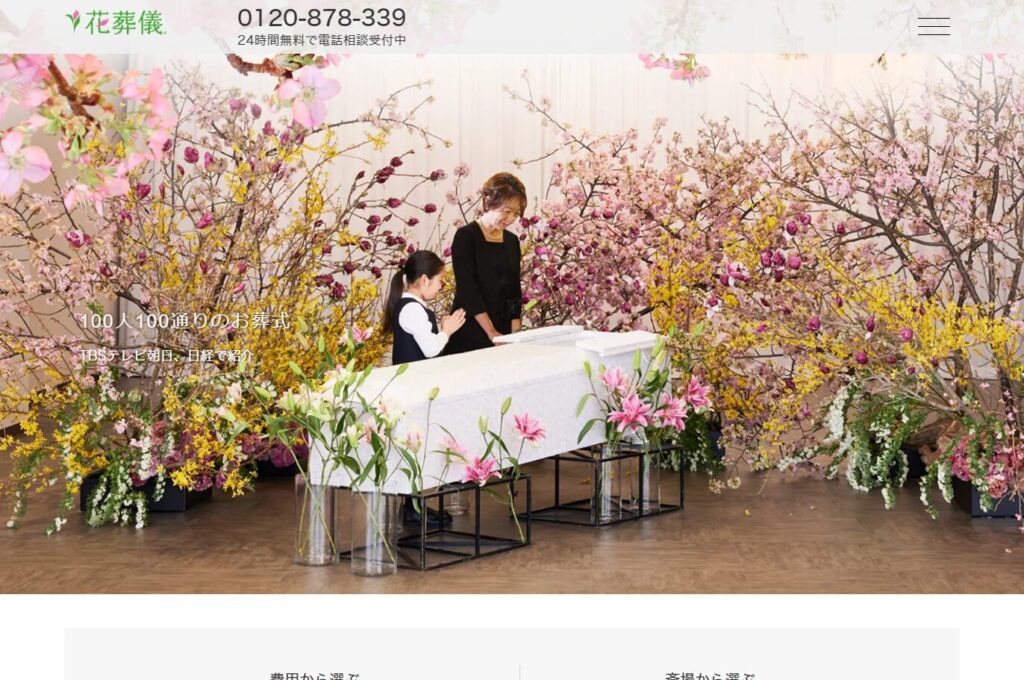
 グランドセレモニー
グランドセレモニー 
 むすびす(旧アーバンフューネス)
むすびす(旧アーバンフューネス)